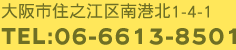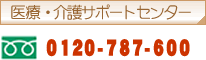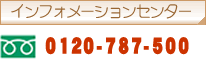|
リハビリ室の窓から(平成21年版)
2009.07.08

長い間ご無沙汰しておりました。申し訳ございません・・・・。
一年二ヵ月ぶりのプログ更新となります。リハビリ科の窓から眺める、
緑あふれる木々の姿は相変わらず、すがすがしいですが、正面のビルもリニューアルし、取りまく状況が変わりつつあります。
このたび、リハビリ科に新しく理学療法士が3名加わりました。
それを機によりよいリハビリの提供を目指して、フロア担当制を導入することになりました。これは、各フロアごとに“顔”
となる療法士を配置することで、日常生活動作や環境設定・ポジショニングなど、
より密接に利用者様と関わることができると考えるからです。また、通所でも待望の個別リハがはじることになりました。
新しいリハビリ科にご期待下さい。
リハビリ科 木村 直樹
リハビリ室の窓から・・・・・
2008.05.21
新緑の色増す季節の五月、いかがお過ごしでしょうか?
リハビリ科の訓練室の窓から見える木々は、実に緑がきれいで、すがすがしいです。
ここでは、大きなガラス窓に木々の葉が、一面に広がって見えます。
季節ごとに彩りを変え、鮮やかに、季節の訪れや、移り変わり教えてくれます。
このようなすばらしい景色を愛でながら、利用者様もリハビリに励げんでいます・・・・。
一度ご覧にいらして下さい。

リハビリ体操
2008.01.16
こんにちは☆ 作業療法士の野澤です!
さて、前回のブログでは、「作業活動って何?」というタイトルで、日々行っている活動を紹介させていただきました。
今回は、「リハビリ体操」についてお話したいと思います。この「リハビリ体操」って、
最近テレビや雑誌等でよくとりあげられていませんか? 少し詳しく説明すると、日常の生活動作がぎこちない方,
肩や膝など運動器官に慢性の痛みのある高齢の方や、関節の拘縮(こうしゅく:固くなる)予防のために筋力強化等を行い、
体力の向上や維持を目的に行う体操のことです。そして、私たちは、ここ雅秀苑での訓練場面で、このリハビリ体操を頻繁に行っています。
体操の内容は、本の内容を基本形として、自分たちで姿勢や使用物品を変えたりしながら、対象者様の身体状況に合わせて考案しています。
例を挙げると、左右の腕力が異なる方のダンベル体操では、左右の重たさに変化をつけて提供したり、片麻痺の方のタオル体操では、
タオルを少し長めにして、麻痺側が落ちないように端を輪にして提供したり、対象者様が現在可能な動きで実施できるように工夫を行っています。
このように、さまざまな対象者様に適応できるように、私たち作業療法士は、疾患の特徴と、
バリエーション豊かな体操の知識をもっておく必要があります。下の写真は、他のスタッフと体操新メニューを考案している風景です。
 
これは、椅子座位での輪を使用した体操で、輪をとってかけるといった「集中力」と前屈姿勢による「腰部周囲柔軟性向上」、起き上がる際の
「腹筋力」を考慮したものです。まだ考案段階ですが、実際に行ってみて、更に改良していこうと考えています。
これからも、疾患に対する知識を積み、どなたでも楽しくなおかつ効果もでるような体操を考案していきたいと思います!!!
高次脳機能学会の紹介
2007.12.13
最近すっかり寒くなり、ここ南港でも夕方になると木枯らしが冷たく吹いています。
リハビリのブログに書かせていただくのも2回目になりました、言語聴覚士の玉元です。
今回は先日、参加してしてきた“高次脳機能学会”について紹介してみようと思います。「高次脳機能」・・・
漢字がとっても多くて難しそうですね。実は最近の流行っている、脳にまつわる専門家の集まりなんです。
高次脳機能とは言語、認知、記憶、注意、遂行機能など人間の脳の中で行われる多くの機能の事を指します。
脳梗塞やその他の病気によってこれらの機能がうまく使えなくなったり、全くできなくなってしまうこともあります。そういった障害に対して、
一緒に集まって発表したり、考えたりする場が「学会」です。
今回、私は聴くばっかりでしたが、経験豊かな多くの先生方の発表や講演を聞くことで、
日々のリハビリに活かせるようなヒントをいっぱい得ることができました。南港に一人しかいないかもしれない言語聴覚士として、
少しでも確かな・質の高いリハビリを提供できるようにこれからも研鑽をしていこうと思っております。
今回の会場近辺の和歌山の街並み

2007年が暮れて行く・・・
2007.12.13
こんにちは。二回目の登場、作業療法士の三浦です。はやいものでもう12月ですね。2007年ももうすぐ終わりを迎えます。
一年の終わりを迎えるという一抹の郷愁とともに今年を振り返ると、私の一年(特に後半)は新しいことへの挑戦の一年だったなと思います。
前々回同僚の日比野が住吉地区の勉強会のことを書いていましたが、その他にも年一回錦秀会グループの職員が集まっていろいろな発表をする
「医療・福祉フォーラム」というものがあります。私たちリハビリ科も今回は初めて演者として発表することになりました。
私個人にとっては共同研究をするのも初めて、
パワーポイントを使って資料を作るのも初めてでまったく段取りもわからず暗中模索の状態でした。
でも徐々に発表の内容が形作られていくうちに、みんなでひとつのものを作り上げるということの面白さや充実感を強く感じることができました。
私はいつも「人生やって無駄なことはない。」という言葉を心に留めながら日々を過ごしています。
新しいことはなにかのきっかけがないと中々始めないものです。初めてのことは戸惑いもあるし、しんどい面もある。失敗することもあります。
でもそれを乗り越えていった先にきっと何か得られるものがあるのだろうと思っています。今年は発表ということを通して新しい考え方・
技術を知り、みんなで一つのものを作ることの難しさ、面白さを知る機会を得られました。これからも毎年少しずつでも新しい物を知り、年々
“成長”できるように努めて生きたいと思います。来年もよろしくお願いします。
外部勉強会での発表経験
2007.12.03
こんにちわ。リハビリ科、作業療法士の日比野です。
ブログ担当2回目がまわってきました!
前回は、雅秀苑でのリハビリ場面のご紹介をさせていただきましたが、ブログ第2段として、今回は、
雅秀苑を出た外での活動の1つをご紹介したいと思います。
この雅秀苑は関連法人である錦秀会の住吉地区の施設に隣接しており、月1回それらの病院や施設のリハビリスタッフと集まり、情報交換、
勉強会を行っています。
ここでは、他院、他施設での近況報告をお互いに行い、リハビリ内容の検討や症例発表などの勉強会を行っています。
勉強会では、毎月交代で各病院・施設に発表する担当がまわってきます。毎回、様々な発表があり、リハビリ活動状況を知れ、
良い刺激になっています。
先月の住吉地区勉強会は、雅秀苑担当でした。私と同期の作業療法士野澤の2人で、発表させていただきました。
内容は、当苑デイケアのリハビリシステムについてです。今回の発表にあたり、1ヶ月前から、内容を考え、まとめたものをスライドにしました。
これが、発表している場面の写真です。

このように、他院、他病院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の前で発表させていただきます。発表後、
質問やコメントなど様々な意見やアドバイスを頂くことが出来ます。
施設内だけでは、考えが偏りやすいですが、第3者からの意見を頂くことで、今後の課題として、リハビリ内容を見直す良い機会となっています。
このように施設内だけでなく、外での活動も、リハビリ業務の一環として行っています。
これからも、当施設の利用者様により良いサービスを提供していけるように、日々頑張っていきたいと思います!!
植物との触れあい
2007.11.08
こんにちは!
作業療法士の佐竹です。
今回は、リハビリの一環として当施設利用者様に対し実施している、「園芸療法」についてご紹介させていただきます。
園芸療法とは、園芸(毎日の水遣りなど植物を世話すること)を中心とした植物に関わる活動を通して、身体や精神機能の維持・
回復を目指し、生活の質の向上を図るリハビリテーションです。認知症の方に対しても、植物を育て手入れする活動を通して、
過去の記憶を呼び起こす手段として優れています。(出展:痴呆性老人のユースフルアクティビティ)
利用者様の中には、若いころから仕事として百姓をされていた方や、趣味で園芸活動を経験してこられた方が多くおられます。
そのような方の持っておられる知識や技術を生かし、植物を育てるという役割を持っていただくことで、自信や自尊心を高め、
当苑での生活の中で生きがいを感じていただいています。

天気の良い日は花がたくさん咲いているベランダへ!
土の感触、花の香り、葉のそよぐ音、色鮮やかな草花・・・
外の新鮮な空気は、色々な感覚を刺激することができます。
 
園芸活動に詳しい方には、鉢植えや挿し木などにも挑戦していただきます。
愛情を込めて丁寧に植えられた草花は、元気に育ってくれることでしょう!
 
決まった時間に水遣りをしていただくことで、日々の生活リズムを整えます。
またこのような昔からやり慣れた動作を行うことや、植物に関する知識を話していただくことで、
過去の回想を促し認知機能を刺激することができます。
「今日はしょんぼりしてるなぁ」
「だいぶ大きくなってきたね」
草花に接する時には、みなさん笑顔で話しかけられます。
今後とも利用者様にもっと喜んでいただけるように、知識・経験を重ねて、サービスの幅を広げるために努力していきたいと思います。
|